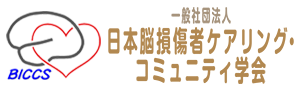代表理事のご挨拶
2023年度の学会の新たな体制
長谷川 幹
世田谷公園前クリニック
2009年、脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会を設立し、2015年、一般社団法人日本脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会と法人化しました。その際の定款に、障害のある人とない人が「同じテーブルで企画・運営し実践する」、「学術研究をする」、「社会に広める」という基本理念があり、年1回の全国大会、主体性研究委員会、機能評価研究委員会、ツール研究委員会、研修委員会、当事者社会参加推進委員会、文化芸術スポーツ委員会、広報委員会の7つの委員会で基本理念を実現すべく活動をしてきました。
この間、筆者が代表を務めてまいりました。発足から10年を超え、筆者の医療職の視点を広げるべく新たな代表を迎えることができました。細田満和子さんは社会学者で彼女の「脳卒中を生きる意味」という本を通じてご縁があり、今回代表理事を一緒にすることになりました。彼女は世界的な活動を展開されており、さまざまな視点を提供していただいています。そして、副代表理事に岡本隆嗣さん、後藤博さん、中村千穂さんが就任し新体制になりました。
世の中の動きはさまざまに展開していますが、これまでの障害のある人とない人がともに企画・運営し実践してきた内容を他の学会や組織などに波及し新たなうねりを起こす時期に来ています。ピアサポーター、高次脳機能障害のある人への支援、コーチングの研修、支援機器、障害のある人のスポーツなどさまざまな普及活動を展開してくことが重要です。
最後に、これらの活動に会員の皆様とともに展開していくことが必須であり、皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。
細田 満和子
星槎大学大学院/東京大学医科学研究所
この度、長谷川幹さんと共に代表理事に就任しました細田満和子です。どうぞよろしくお願いいたします。社会学や公衆衛生学が専門で、普段は大学で教えたり、研究したりしています。病や障がいがあっても自分らしく生きられる共生社会を実現するため、いかなることが障壁になっていて、どのようにしたら乗り越えられるのかということを、当事者の皆様と共に考えていきたいと思っています。
今、国の内外において様々な危機が生じています。地球環境や平和が脅かされ、人命が損なわれ、極度の緊張を強いられている人々の暮らしが、いたるところで見受けられます。こうした状況の下で、人々の<生きる>を守り生き抜くためには、異なる他者を認め、互いに尊重し合うことがますます必要になってきます。
本会には、立場の違いを超えて、誰もが人として尊重され、共に生きることが可能な社会に向けて、行動を起こしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。近年、DE&I(Diversity, Equity and Inclusion=多様性、公正性と包摂性)の重要性が指摘されています。これは、本会が2015年に設立された時から掲げている理念と共通するものだと思います。
皆様と学びあいながら、皆様と共に、こうした世界を創り上げることに資する活動ができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。